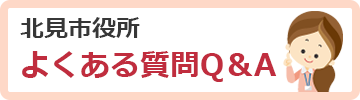MENU
CLOSE
北見未来創発プロジェクト(第3期)
R6.8.24(土) 第1回目 『開講式・オリエンテーション』
イントロダクション
参加者に向けた北見未来創発プロジェクトの趣旨説明を行った。
テーブルワーク・ディスカッション
参加者それぞれが人生グラフ、自己紹介シートを作成し、それをもとに行った自己紹介によって、お互いの人物像について理解を深めた。
その後、「これからのありたい姿」について、グループでディスカッションを行い、北見未来創発プロジェクトを通じて、成し遂げたいことを参加者同士で共有した。


R6.9.14(土) 第2回目
ローカルゼブラと外貨獲得
現在注目されているローカルゼブラ企業(利益を追求するだけでなく、地域社会に根差した事業活動を行い、地域の課題解決と持続可能な経済発展を目指す企業)と外貨獲得のための「差別化」について理解を深めた。
事例紹介
オホーツクで外貨獲得に向けた活動を行う企業の方々にお越しいただき、活動内容を紹介していただいた。 【株式会社グリーンズ北見 ・ 株式会社秋山工房 ・ 株式会社山上木工】



ディスカッション・ワークショップ
参加者同士でディスカッションを行い、自身の事業でどのように外貨を獲得することができるのかを話し合った。また、お互いの事業を掛け合わせ、新たな商品やサービスの開発することでの外貨獲得の可能性を見出した。


R6.10.4(金) 第3回目
CSVと地域課題解決
CSV(企業が社会(地域)のニーズや社会課題を解決する事業に取り組むことで、社会的価値を創造し、結果、経済的価値(企業の利益)が創造されること。)の概念と地域課題とビジネス創出の可能性について理解を深めた。
事例紹介
実際にCSVの概念を取り入れた事業を行っている株式会社エース・クリーン様にお越しいただき、事業内容を紹介していただいた。

ディスカッション・ワークショップ
北見市やオホーツク全体の地域課題について参加者全員で分析し、それぞれの事業に関連する地域課題をまとめ、どのように解決に導くことができるかを話し合った。


R6.10.25(金) 第4回目
ローカルバリューチェーン
ビジネスの付加価値と差別化要素を生み出すバリューチェーンのフレームワークの基礎と、ローカルにおけるバリューチェーン活用の手法について、地域の具体的な事例を取り上げながら理解を深めた。
ワークショップ
自社の取組に対して、現在どのようなバリューチェーンとなっているかを分析することに加え、差別化や付加価値化を進めるためのバリューチェーンの強化、カスタマイズについてディスカッションを行った。


R6.11.15(金) 第5回目
マーケティングとデザイン戦略
ローカルの中小企業において基本戦略となる差別化戦略を実現する上で重要となるフレームワーク、3C(市場・顧客【Customer】、自社【Company】、競合【Competitor】)に関する基礎知識と、3Cに地域ならではの強みを加える3C+C(協力者・地域課題【Collaborator・Context】)のフレームワークについて理解を深めた。
事例紹介
第2期北見未来創発プロジェクトの卒業生でもある株式会社ツムラの津村健太氏にお越しいただき、地域とのつながりによる差別化戦略と、自社の事業分野転換における具体的な変遷について講義をしていただいた。

ワークショップ
自身の好きなブランドや商品・サービスをテーマとした3C分析を通じてフレームワーク活用のトレーニングを行った上で、自社の取組の差別化に向け、3C+Cの目線でビジネスモデルの検証を行った。


R6.12.7(土) 第6回目
ロジカルシンキング
ビジネスにおける問題解決手法として、ロジカルシンキングのフレームワークについて学び、重要な観点となるMECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略語であり、「お互いに重複せず、全体として漏れがない」という意味)や因果関係の観点に加え、理想と現実の分析手法、ロジックツリーによる問題分析手法について実例を取り上げながら理解を深めた。
ワークショップ
ロジカルシンキングのフレームワークを活用し、現在考えているビジネスの理想像を起点とした問題分析と課題化を行った。
また、ビジネスの内容について参加者同士の共有や支援機関からのフィードバックを行い、内容の精度を高めた。


R6.12.21(土) 第7回目
ビジネスプランの作成
今回から3回にわたるビジネスプラン作成の演習を進めるにあたり、地域課題解決や地域資源活用、域内連携等の手法を取り入れた事業内容をブラッシュアップするため、演習シート(これまで学んできた内容を再考し、事業内容等をまとめるもの)の作成を始めた。
ワークショップ
各自のプランニングの方向性に対し、参加者と支援機関からアイデアやアドバイスを付箋に書き出し、共有することで構想のブラッシュアップを行った。
また、今後進めるプランに対して、コンセプトを一行で表現し、参加者同士で共有を行った。
R7.1.17(金) 第8回目
プレゼン練習
各自が準備した資料をもとに最終発表を意識した5分間のプレゼン練習を行った。
その後、質疑応答や意見交換を行い、改善点を洗い出すことで、今後のプラン作成に対するヒントを得た。
(支援機関からのアドバイス)
・事業の対象となるターゲットが絞り切れていない
・効果的な情報発信(周知)の方法を練り直す必要がある etc
ワークショップ
プレゼン練習での意見を踏まえ、各自で内容を振り返り、事業プランのコンセプトを100字程度で要約した後、共有を行った。
R7.2.7(金) 第9回目
プレゼン練習
前回のアドバイスを参考に、各自修正を加えた資料を使って、最終発表に向けた最後のプレゼン練習を行った。
その後、支援機関から具体的な意見や指摘を受け、より洗練されたプランを作成するためのヒントを得た。
(支援機関からのアドバイス)
・実現可能な事業であるかを示す根拠として、定量的な内容(売上目標など)を資料に組み込むべきである。
・専門的な内容が多いため、図や写真を使いながら説明し、聞き手がイメージしやすいようにすべきである。 etc
R7.3.1(土) 第10回目 『成果報告会』
開会


参加者プレゼンテーション
1.北見の木工によって北見のいろいろをより価値のあるものとして魅せよう
発表者:工房ホリタ 堀田 雅大 氏
自社課題として置物に偏重したものづくりと将来的な売上に関する課題があり、食品を中心とした地域のメーカーにおいては展示会等での装飾と、それによる販売促進に関する課題がある。そのような中、展示する商品の良さを引き立てる展示用の木工製品を企画製造し、自社課題と地域課題の解決に向けた事業をプランした。

2.マーケ機能付きWebサイトで、全国展開×地元協業による成長プラン
発表者:(株)ウィズプランニング 塩浜 涼一 氏
自社課題として、Webサイト制作事業の将来的な売上や利益率に対する課題がある一方、全国的な傾向として、ECサイトによる販売金額が首都圏に集中しており、地方都市にとってメリットのあるはずのネット販売のシェアが地方都市では低いということがわかった。そのような中、今後の事業として、ワンストップでECサイトのマーケティングを可能とするITツールを開発し、全国的な導入を進めることで地方都市のEC販売金額を向上させるだけでなく、地域におけるIT人材の雇用を創出する。

3.北見インド大使チャーリー 新感覚『食べるラッシー』発売への道
発表者:チャーリーワークス 野田坂 敦子 氏
現在、インドに対して専門性やネットワークを持っており、オホーツクの資源と、自身の知識とネットワークを活かした製品開発として、オホーツクの酪農家、研究機関と連携し新しいラッシーを開発する。また、開発した商品をインドと北見の架け橋として用い、今後さらに成長していくインドと北見の人的、経済的繋がりを強化することで、地域振興に繋げる。

4.MILK CROWN オホーツクから世界へ
発表者:(株)アース興建 織田 賢 氏
これまで、自社の牧場で生産された牛乳を使い、アイス製造に着手しており、今後さらなる販路拡大、販売の拡大を目指している。そのような中、差別化の課題を感じており、オホーツクの飼料を活用することや、差別化のための機能的要素の付加、パッケージを中心としたマーケティングをブラッシュアップすることで、国内の大手流通に対して販路開拓し、販売額を高めていく。

5.Mottainaiを価値に変えていく、地域の食品コンサルティング業
発表者:流氷の丘カンパニー 武内 純子 氏
現在夫婦で酪農業、6次メーカーとして、商品製造、販売販促等を行っている中、自身の技術、キャリアとして、食品加工に対する専門性を有しており、様々なメーカ-からの相談を受けているが、その多くが無料相談となっており、ビジネス化に対する課題がある。一方で、地域のメーカーに対しては、コンサルティングにより商品価値を向上させ、販売を向上させることで地域としても付加価値額を高められる可能性があり、今後、地域の食品コンサルティング業としてビジネスモデルを作り、自社としても、クライアントに対しても価値提供していく。

6.「心温まる時間をつむぐサポートタクシー」~withコロナ時代を安心してご利用いただくために~
発表者:ライフケアタクシーロコ 松山 隼也 氏
コロナ禍において、ほぼ全ての介護施設において面会が制限され、たくさんの家族にとって不自由な状態となってしまった。現在も様々なウイルスへの対策として面会には一定の規制がある中、家族が思う存分触れ合うことができる介護タクシー事業を計画し、単純な移動補助だけではない、家族が触れ合うことに着目し差別化されたサービスの提供を進めていく。

7.北見に残る選択肢を増やせ!カーシェアでつなぐ企業と学生
発表者:(株)Skyward Growth 藤本 大地 氏
現在、学生起業家として、大学生ユーザーとしてカーシェア事業に着手しているが、学生の数や利用機会が限られる中、利益率を高めるサービス設計の課題がある。一方で、地域においては卒業後の学生の域外流出や、企業における採用難といった地域課題があり移動を通じて企業と学生の結びつきを強め、地域への人材定着を図る新たなサービスを企画する。

8.「WLAIA」リカンベント型のEVスクーターの製作販売
発表者:北見工業大学 三石 楽 氏 (当日欠席により、動画による発表)
北見工業大学で機械について学び、ロボット開発や3Dモデリングの技術を身に着けている。大学発ベンチャーとして、新たな乗り物の開発を検討しており、薄利多売ではなく、少数でも利益を出しながら、地域らしい差別化要素を持ったEVスクーターの開発、製造、販売プランを計画する。
9.シズル感で集客ワークショップ
発表者:北陽スタジオ 小田切 巧 氏
人口減少が進む中、自身の写真店の顧客や売上は減少傾向にあり、今後もさらに人口減少が進んでいくことから、新たなサービス開発による売上確保の課題がある。北見市には多くの飲食店がある一方で、写真撮影技術は低く、改善することにより、地域に新たな客を呼び込むことや、消費拡大に繋げられる可能性があり、飲食店においては売上拡大の余地がある。自社の新たなビジネスとしてこれまで培った写真撮影技術をスクール形式で店舗に提供することで、自社と飲食店、両者の売上拡大を図る。

10.本当!?の北見焼肉を体験 焼肉公園実現構想
発表者:(有)杉商 杉田 裕樹 氏
現在焼肉店を経営しているが、席数と稼働から、売上の限界を感じており、新たな収益機会を模索している。北見市においては焼肉の街としてのブランドがあり、今後焼肉を目的とした観光客誘致の課題がある。そこで新たなサービスとして公園での焼肉ケータリングサービスを計画し、新たな収益の確保と、焼肉の街としての体験の受け皿を作ることで、観光振興を図る。

11.「有機の窓口」有機農業の一大産地を目指して
発表者:(株)一戸農業 一戸 宏公 氏
現在畑作を中心とした農業を経営しているが、限られた土の生産性や農地を最大限に活用し、新たな就農を促しながら持続的な地域農業を実現していく手段として、有機農業に取り組んでいる。現在、ごく限られた戸数で有機農業に取り組んでいるが、より多くの農家と技術を共有し、販路を共有していくことで生産性を高め、より持続的なモデルをつくることができると考えられ、事業化に向けたプランを作成する。

講評





集合写真

| お問い合わせ |
|---|
| 商工業振興課 産学官連携担当 電話:0157-25-1148 |