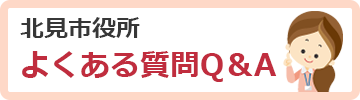MENU
CLOSE
常呂の遺跡:岐阜第二遺跡
岐阜第二遺跡

岐阜第二遺跡は「岐阜台地」と呼ばれる台地上、標高約10~16mの地点にあります。台地の北側の縁に広がっており、ライトコロ川が流れる低地に面する場所となっています。小さな沢が流れる谷があり、その周辺を中心として多数の竪穴住居跡が見つかりました。
この遺跡では1965年、1966年、1976年の3回にわたって発掘調査が行われており、縄文、続縄文、擦文の各時代にわたって集落があったことが明らかにされています。また、常呂地域では現在唯一の旧石器時代の遺跡が見つかっている場所でもあります。
| 遺跡名 | 岐阜第二遺跡 (ST-02遺跡) |
|---|---|
| 所在地 | 北見市常呂町字岐阜 |
| 立地 | ライトコロ川が流れる低地に面した台地上、標高約10~16m |
| 時代 | 旧石器・縄文・続縄文・擦文 |
| 遺構・遺物 | 竪穴住居跡・土坑(縄文・続縄文・擦文)、石器集中部(旧石器) 土器・石器・金属製品 |
| 現況 | 畑地など |
| 文献 | 東京大学文学部考古学研究室 1972 『常呂』 藤本 強・宇田川洋 編 1977 『岐阜第二遺跡:道営畑総事業に伴なう事前調査報告』 藤本 強・宇田川洋 編 1982 『岐阜第二遺跡:1981年度―私道建設に伴う事前調査』 |
岐阜第二遺跡の遺構と遺物

岐阜第二遺跡は、旧石器時代の遺跡としては北見市の沿岸部で発見された唯一の遺跡です。北海道全体で見ても旧石器時代の遺跡は内陸部を中心に分布し、海岸部の地域では少ないため、少し珍しい立地にある遺跡と言えます。
出土している石器も少し変わっており、北見市の内陸部の遺跡では半数以上が黒曜石で作られていますが、この岐阜第二遺跡では黒曜石が全く使われず、頁岩(けつがん)という白色の石が使われています。
これらの石器は、本来の包含層と見られるローム層中では2.5m×2mの範囲にまとまるかたちで出土しており、当時の人が石器を作るためにこの場所で石を打ち割り、不要な石器や石の破片を置き去りにしていったものと考えられます。
この遺跡がいつ頃残されたものなのかについては、はっきりした証拠が残っているわけではありませんが、他の遺跡との比較から24000~25000年前頃にさかのぼるものと推定されています。
続縄文時代の遺構と遺物


続縄文時代のものと推定される遺構は竪穴住居跡3基、土坑約20基が発掘されています。出土遺物から見て、続縄文時代前半期の宇津内IIb式のものが中心となるようです。
土坑のうちいくつかは墓と見られるもので、副葬された土器や石器が見つかっています。中でも「ピット28」と呼ばれる土坑から見つかった土器は特徴的なものです(写真)。宇津内IIb式と呼ばれる道東部で作られてきたタイプの土器と、後北C1式と呼ばれる道央方面から伝わってきたタイプの土器の2つの土器が一緒に見つかったもので、後北C1式土器を宇津内IIb式土器の中に重ね入れた状態で置かれていました。後北C1式土器はクマの頭部をデザインした突起が4つ付く、珍しい形のものとなっています。
「ところ遺跡の森」の関連ページ
| お問い合わせ |
|---|
| 北見市教育委員会社会教育部 ところ遺跡の森 郵便番号:093-0216 住所:北海道北見市常呂町字栄浦371番地 電話:0152-54-3393 FAX:0152-54-3538 |
お問い合わせは下記フォームをご利用ください
教育・文化
教育委員会
教育委員会
その他
スポーツ
- 東陵公園(スポーツ施設)の利用料金を改定します
- 北見市立体育センター及び市民トレーニングセンターの利用料金を改定します
- 北見市民スケートリンクの利用料金を改定します
- 北見モイワスポーツワールドの利用料金を改定します
- 北見市民温水プールの利用料金を改定します
- 北見カーリングホールの利用料金を改定します
- 北見市武道館の利用料金を改定します
- 八方台スキー場のリフト料金を令和7年10月1日より改定します
- 八方台森林公園の利用料を令和7年10月1日より改定します
- 留辺蘂町旭運動公園の利用料を令和7年10月1日より改定します
- 留辺蘂町体育館の利用料を令和7年10月1日より改定します
- 留辺蘂町格技場の使用料および留辺蘂町弓道館の利用料を令和7年10月1日より改定します
- 北見市公共施設予約サービス
- 北見市留辺蘂町八方台スキー場 安全報告書
北見市のスポーツイベントは?
スポーツをする場所は?
スポーツを教えてほしい!
スポーツの指導者になりたい、学びたい!
補助金制度
スポーツの豆知識
寄付等
その他
青少年
児童館
育成
相談指導
その他
学校教育
学校教育
学校一覧・行事一覧
部活動の地域移行
学校閉鎖・臨時休校
北見市の給食
その他
教科用図書採択関係
市立学校の通学路
調査結果
就学手続き
文化施設
北見自治区
- 埋蔵文化財保護のための事前協議に関する届出
- 北見市西地区公民館
- 北見市北地区公民館
- 北見市東地区公民館
- NiCC芸術文化ホール(北見芸術文化ホール)の利用料金を改定します(令和7年10月1日から)
- 北ガス市民ホール(北見市民会館)の利用料金を改定します(令和7年10月1日から)
- 【北見自治区】北地区公民館、東地区公民館、西地区公民館の使用料を改定します(令和7年10月1日から)
- 北見芸術文化ホール(愛称 NiCC芸術文化ホール)
- 北見市民会館(愛称 北ガス市民ホール)/北見市中央公民館
- 北見市公民館の紹介
- 北見芸術文化ホールの新愛称は「NiCC芸術文化ホール」に決まりました!
- 北見市民会館の新愛称は「北ガス市民ホール」に決まりました!
- 北見市公民館運営審議会の活動
- SL広場
- 美里洞窟(公開中止)
- ピアソン記念館
- 北見ハッカ記念館・薄荷蒸溜館
- 北網圏北見文化センター
端野自治区
常呂自治区
留辺蘂自治区
その他
姉妹友好都市・国際交流
北見市の姉妹友好都市
国際交流
生涯学習
ミント宅配便
- 市民編講座No.250「体を整え、呼吸を整え、 心を整える 」「コアチューニング®体操」
- 市民編講座No.247「篆刻」(楽しい篆刻講座・石に字や名前を彫ってみませんか)
- 市民編講座No.245「経木クラフト」
- 市民編講座No.225「スマイル介護教室」
- 市民編講座No.223「身近にいる小さな命を 探してみよう ~野鳥観察入門~」
- 市民編講座No.221「もっと身近に 腸内細菌のお話」
- 市民編講座No.220「健康について ~大きな病気を経験した 私から皆さんに伝えたいこ と~」
- 市民編講座No.218「ユニバーサル デザインの世界、 色の多様性を知ろう!」
- 市民編講座No.217 私らしい子育ての ヒントが見つかる 「私の“大切な”子育て観 ワークショップ」
- 市民編講座No.215「本」を 作ってみませんか?
- 市民編講座No.207「江戸の文化史」
- 市民編講座No.206「日本の占いの歴史」
- 市民編講座No.258「あっと驚く、不思議で楽しいマジック」
- 市民編講座No.201「教養としての民法とカウンセリング」
- 市民編講座No.259 現代調の創作「講談」を聴いてみませんか
- 市民編講座No.257 ファミリー劇場「たんぽぽ」の公演
- 市民編講座No.256 子どもも大人も「紙芝居」をみて平和と命の大切さを考えよう
- 市民編講座255「オカリナの素朴で優しい音色を聴いてみませんか」
- 市民編講座No.254「オカリナの音とともにうたとリズム遊び」
- 市民編講座No.249「太極拳入門」
- 市民編講座No.248「ラジオ体操・みんなの体操で健康づくり」
- 市民編講座No.246「心を解き放つ 己の書」
- 市民編講座No.244「折って遊ぶ 折って飾る 脳活折り紙」
- 市民編講座No.242「ヘタでいい ヘタがいい楽しい絵手紙」
- 市民編講座No.241「一緒に木版画を楽しみましょう」
- 市民編講座No.240「つまようじで絵を描こう!」
- 市民編講座No.239「園児から高齢者までみんなで楽しく詩吟教室」
- 市民編講座No.238「歌は友達!みんなで楽しく~歌唱指導~」
- 市民編講座No.237「ご一緒に、パンをつくりませんか!」
- 市民編講座No.236「おいしいコーヒーの入れ方」
- 市民編講座No.235「茶道を身近に」
- 市民編講座No.234「災害時に役立つ登山技術と登山用品とは?」
- 市民編講座No.233「避難所生活になったら?(模擬体験しておこう!)」
- 市民編講座No.230「防災・減災のためにできることとは何?」
- 市民編講座No.229「みんなで助け合う自主防災活動とは!」
- 市民編講座No.227「カードゲームで探る、私の“価値観”ワークショップ」
- 市民編講座No.226「心に効く!色とぬりえの 小さな魔法」
- 市民編講座No.224「障がいと共に生きる」
- 市民編講座No.222「北見の自然と風土」
- 市民編講座No.219「~体にいいこと~免疫力アップのために」
- 市民編講座No.216「元看護師の産前産後楽ママ講座」
- 市民編講座No.214「え、そんなに関係あるの?知らずに使ってる色のチカラ」
- 市民編講座No.213「カルト宗教、霊感、占い商法に騙されないために」
- 市民編講座No.212「高島暦の読み方と活用」
- 市民編講座No.211「人生設計の考え方~夢の叶え方教えます!~」
- 市民編講座No.210「北見」を書いた作家たち
- 市民編講座No.209「下の句百人一首(カルタ)を楽しみましょう」
- 市民編講座No.205「じゃがいものひみつ」
- 市民編講座No.204「もっと、アグリエイティブに!~北見の農業と肥料の話~」
- 市民編講座No.203「国際理解を深めよう!」
- 市民編講座No.202「最近物忘れがある‼私の財産は大丈夫?~後見制度について~」
- 市民編講座No.231「災害から身を守るためにしておくことは何?」
- 市民編講座No.228「カーリングって楽しい⁉そだねぇ~‼カーリングを100倍楽しむ徹底ガイド」
- 市民編講座No.253「ポップス尺八と民謡」
- 市民編講座No.251「フランス生まれのボールゲーム(ペタンク)を楽しみましょう」
- 市民編講座No.252「やさしい合(愛)氣の施術」
- 市民編講座No.243「楽しい”きり絵”」
- 市民編講座No.208「北方領土語り部講座」
- 出前講座「ミント宅配便」
生涯学習
- 第45回(令和7年度)北見市女性国内研修「まとめ」
- 端野陶芸工房の使用料を改定します
- 端野生涯学習カレンダー 気になるイベントにぜひご参加を!
- 令和7年度「伝統文化子ども教室」実施希望団体の募集
- 北見市マイプラン・マイスタディ事業に関する申請
- 令和7年度 北見市社会教育委員の会議
- 市民編講座No.232「防災用品として何を準備しておくと良いのだろう?(備蓄品とその数量は?)」
- 施設ガイド
- 開成ふるさと工芸館
- 地域おこし協力隊「生涯学習サポート隊」です!
- 第3次北見市社会教育計画
- 北見市スポーツ・文化等振興補助金に関する申請(生涯学習関係)
- 家庭教育
- 端野しらかば大学
- 生涯学習事業補助金
- 端野しらかば大学 年間の活動紹介
- 放送大学北見学習室
- 第44回(令和6年度)北見市女性国内研修「まとめ」
- 令和6年度 北見市社会教育委員の会議録
- 高齢者大学「北見ことぶき大学」の活動
- 第43回(令和5年度)北見市女性国内研修「まとめ」
- 令和4年度 北見市社会教育委員の会議録
- 令和3年度 北見市社会教育委員の会議録
社会教育部事業等収録
その他
生涯学習ガイドブック
補助・助成
歴史・風土
北見自治区
端野自治区
常呂自治区
- 「ところ遺跡の森」便り【2025年10月~】
- ところ遺跡の森:資料のダウンロード
- 大島1遺跡:2024年・東京大学の発掘調査
- 「ところ遺跡の森」便り【2025年4月~9月】
- 常呂町史の販売
- 遺跡の森デジタルミュージアム【簡易版】
- 常呂の遺跡:大島2遺跡
- 常呂の遺跡研究史
- 遺跡の森・植物案内
- 「郷土ところ」復刊(常呂町郷土研究同好会発行)No.13からNo.24まで
- 「郷土ところ」復刊(常呂町郷土研究同好会発行)No.1からNo.12まで
- 北見市教育のあゆみ(旧常呂町)
- 「郷土ところ」復刊(常呂町郷土研究同好会発行)No.49からNo.62まで
- 「郷土ところ」復刊(常呂町郷土研究同好会発行)No.37からNo.48まで
- 「郷土ところ」復刊(常呂町郷土研究同好会発行)No.25からNo.36まで
- 史跡常呂遺跡の世界遺産暫定一覧表記載資産候補に係る提案書
- ところ遺跡の森:ところ埋蔵文化財センター
- ところ遺跡の森:図書(図録)販売のご案内
- 国指定重要文化財「常呂川河口遺跡墓坑出土品」
- 大島2遺跡の発掘調査
- 「ところ遺跡の森」便り
留辺蘂自治区
講座・催し
講座情報
端野自治区