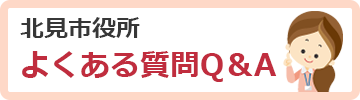MENU
CLOSE
「ところ遺跡の森」便り:遺跡の森の自然
早春の花
4月には遺跡の森でもようやく雪が姿を消し、春の花が咲く季節になりました。毎年雪解けと共に咲き始めるのがキタミフクジュソウやアズマイチゲです。
黄色い花のキタミフクジュソウは近年、数の減少が心配されている稀少な植物ですが、遺跡の森では群生している箇所がいくつかあります。今年はキタミフクジュソウの花は4月末まで、アズマイチゲは5月はじめまで見ることができました。日が出ていないときには花は閉じてしまうので、晴れた日に見るのがおすすめの花です。
4月~6月はさまざまな花が見られる季節です。5月にはこれらの花と入れ替わるようにして、オオバナノエンレイソウが遺跡の森・擦文の村周辺ほかで一面に咲いています。5月20日過ぎころまでが見ごろです。(2015年5月)


エゾシマリスの食事
2015年は全道的にドングリが不作のようです。遺跡の森でも例年大量に実るはずのドングリが今年はあまり落ちていません。餌の減少で、ヒグマの被害が心配されていますが、ドングリはヒグマだけでなく森の様々な動物の食料となっています。
遺跡の森に住むエゾシマリスもドングリを餌にしています。おなかをすかせているのかと思いきや、ドングリがなければ他の木の実から虫まで色々なものを食べているようです。遺跡の森にはハマナスが生えている場所がありますが、いつの間にか実がなくなってしまいました。トゲだらけのハマナスに平気でよじ登る姿も目撃されており、かなりの量をシマリスが食べてしまったようです。他に、カエデの実を集めているところも見つかっています。
シマリスは冬が来る前に食料を集めておかなければならないので今、大忙しです。遺跡の森で彼らを見かけた場合は、驚かせないようにそっと見てあげてください。(2015年11月)


冬の遺跡の森でみられる野鳥
冬になると遺跡の森はしばらく雪に覆われる季節になります。草木の多くは葉を落とし、シマリスなどの動物は冬眠に入ってしまうため、森の中は一見さびしくなってしまいますが、そうした中でも元気に活動している鳥たちがいます。
見つけやすい鳥としてはキツツキの仲間がいます。木の幹を歩きながらエサを探して小刻みに木をつつく音を立てるので探しやすい鳥です。よく見られるのはアカゲラで、背が黒、腹が白でお尻の赤い鳥です。まれには国の天然記念物にも指定されているクマゲラが見られることもあります。
最も多くいるのはカラ類の鳥です。ハシブトガラ、ゴジュウカラ、シジュウカラ、ヤマガラといった鳥で、別々の種類の鳥なのですがこの季節は一緒に群れて生活しており、にぎやかなさえずりを聴くことができます。中でもゴジュウカラはキツツキより木を歩くのが得意な鳥で、垂直な壁でも上下自在に歩くことができます(写真)。
遺跡の森ではウェブサイトで実際に見られる鳥の一部を写真で紹介していますので、機会があれば見てみてください。(2016年1月)


雪上の足跡
今冬は雪が早く積もり始めました。遺跡の森も昨年末からすっかり雪に覆われています。この季節には冬眠に入る動物も多いですが、雪の上で元気に活動する動物もいて、たくさんの足跡が残されるようになります。
最もよく見かけられるのはエゾシカとキタキツネの足跡です。
エゾシカは体が大きく重いため、2つに分かれた蹄(ひづめ)の跡が深く、くっきり残ります。春になると群れをつくりますが、この季節は群れずに行動しているようです。
キタキツネの足跡は4本の指の跡と足底が梅の花形に並んだ形です。同じイヌ科のエゾタヌキも似た形、大きさの足跡ですが冬にはあまり歩き回らないので、多くの場合はキタキツネの足跡と見て良いようです。雪の上で餌を探すためか、縦横に動き回った活発な足跡を見ることができます。
この他、ネズミの足跡が見られることもあります。目立たないせいか目につくことは少ないですが、小さな足跡と一緒に細長い尻尾を引きずった跡があるのが特徴です。
冬の森では鳥以外の動物を目にすることが少なく、一見さびしく見えますが、雪の上に注目すると少し違った趣を感じることができます。(2017年2月)

キタキツネの足跡

雪の上を縦横に走る足跡
遺跡の森のネズミたち
2020年の干支はネズミですが、遺跡の森にも何種類かネズミの仲間が住んでいます。狭い意味でのネズミの仲間(ネズミ目[もく]ネズミ科[か])としてはエゾアカネズミやドブネズミ、またこれに近い仲間ではエゾヤチネズミ(ネズミ目[もく]キヌゲネズミ科[か])などが目撃されています。これらより一回り小さいトガリネズミという動物もすんでいますが、こちらは正確にはモグラ等の仲間(トガリネズミ目(もく))です。
ネズミの仲間は小さくすばしこく、さらには夜行性だったりするため、遺跡の森で実際にその姿が見かけられることはあまりありません。ところが、冬になって雪が積もるとあちこちに足あとが残るため、姿を見ない動物の存在も分かるようになります。雪の積もった森の中で探してみると、ところどころに小さな足あとを見つけることができます(写真)。ネズミの仲間は飛びはねて移動するので、足あとの歩幅が大きくなっています。しばしば尻尾を地面にひきずるため、両足の間にそのあとがつきます。結果として、細長い線の両側に点々と足あとが並ぶ形になるわけです。
時にはこれにキタキツネの足あとが重なっていることがあります。獲物を探していたキタキツネに見つかって、追いかけっこになったようです。このネズミは無事に逃げられたのでしょうか…?(2020年2月)


ヤマブドウ
遺跡の森では紅葉の季節に黄色から橙色になる葉が多い中で、ところどころに真っ赤な葉の木も混じっています。その多くはヤマブドウの木です。
ヤマブドウには雄株と雌株があり、雌株だけが実をつけます。遺跡の森にはヤマブドウの木が多く見えるわりに、実のなる木はあまりありません。ヤマブドウは実が小さく種子が大きかったり、酸味が強かったりするため、現代の栽培種のブドウと比べてしまうと美味とは言えません。けれども、遺跡からはヤマブドウと見られる種子が発見された事例があり、大昔から利用されてきたことが窺えます。
常呂では、特にアイヌ文化期(14~19世紀ころ)の遺跡でまとまって見つかっています。常呂川河口(ところがわかこう)遺跡では「物送り場」(動物の骨や植物の種子、灰などを集め、祭った場所)からヤマブドウの種子が見つかりました。また栄浦第一(さかえうらだいいち)遺跡では墓から510粒もの種子が見つかりました。ヤマブドウの実を副葬したものかもしれません。
さらに、大島2遺跡では擦文(さつもん)時代後半・12世紀の竪穴住居跡からブドウの仲間と見られる種子が見つかっており、ヤマブドウの利用はアイヌ文化期以前にも辿れそうです。
現代ではジュースやワインに加工して楽しまれているヤマブドウですが、古くから秋の味覚として親しまれてきたものだったのです。(2020年11月)


遺跡の森のキビタキ
遺跡の森では数多くの野鳥が暮らしています。暖かい地方で冬を越した鳥も5月頃から北海道に帰ってきており、あちこちでさえずりを聞かせてくれるようになりました。遺跡の森ではこうした夏鳥の中でも、センダイムシクイ、アオジ、ヤブサメなどの声をよく耳にします。
キビタキはそうした夏鳥の1つです。幼鳥やメスは褐色の地味な姿をしているそうですが、成鳥のオスは黒い頭・背と黄色い胸のコントラストが鮮やかな姿で、さえずりの美しさでも知られています。キビタキのさえずりは「ピッコロロ」とか「オーシツクツク」などと表現されることがありますが、こればかりは実際に聞いてみないとよく分からないと思います。遺跡の森にいる夏鳥の中ではひと際高い音でさえずることが特徴です。
さえずりは縄張りを主張したり、メスを呼んだりするためのもので、繁殖期の夏だけに聞くことができます。毎年歌い始めの5月中頃から聞いていると、不完全なさえずりからだんだん調子が整っていくのが分かります。鳥によってさえずりの音程に違いがあったり、途中で調子がくるったりすることもあるようです。キビタキの中にも、歌の上手・下手があるのかもしれません。(2021年6月)

以下のページでは、遺跡の森で録音されたキビタキのさえずりを聞くことができます。どのように聞こえるでしょうか? 実際に聞いてみてください。
「遺跡の森」に咲くスミレの仲間
遺跡の森では、4月末から6月前半にかけて、多くの草花が見られます。今回はその中から、スミレの仲間を採り上げてみます。
遺跡の森で見られるスミレの仲間にはスミレ、ミヤマスミレ、アイヌタチツボスミレ、アカネスミレ、オオバタチツボスミレ、オオタチツボスミレ、エゾノタチツボスミレ、ツボスミレなどがあります。この中から、5月末から6月初め頃に見られる代表的な4種類をご紹介します。
オオタチツボスミレは径約2cmの紫色の花を付けます。丈が低く、大きくても20cm程度までですが、ひとかたまりに密集して咲いていることが多い種類です。見た目はアイヌタチツボスミレとよく似ていますが、アイヌタチツボスミレは開花時期が早く、5月半ばころには花が終わってしまいます。

エゾノタチツボスミレはオオタチツボスミレよりも丈が高めで、30cmくらいになっているものもあります。径約2cmの薄紫色の花が咲きます。

オオバタチツボスミレも、エゾノタチツボスミレと同じくらい丈が高くなります。ここでご紹介しているスミレの中では、最も大きな花が咲く種類で、径3cm近くにもなります。青紫色の地に、濃い青紫色の筋が入る花で、鮮やかな色彩がひときわ目を惹きます。

ツボスミレは、今回紹介する中では最も小ぶりで、ほとんどの場合、高さ15cm以下です。あまり目立たず、周りにほかの植物があると見つけにくいかもしれません。径約1cmの、白っぽい色の花を付けます。

かなり簡単にご紹介しましたが、スミレの仲間は種類が多く、上記以外のものが咲いていることもあります。機会があれば、少し注意して見てみてください。
スミレの仲間は多年草なので、無事に年を越せば同じ場所に花を咲かせてくれます。ただし、踏まれると弱ってしまい、葉や茎が生えてこなくなってしまいます。背が低く、目立たない種類も多いですが、花を見つけたら大切に見守るよう、ご協力をお願いします。(2022年6月)
遺跡の森のリス
北海道にはエゾリスとエゾシマリス、2種類のリスの仲間がいます。遺跡の森では以前からエゾシマリスが暮らしており、時折人目に触れる場所に姿を見せてくれることもあります。エゾシマリスは名前の通り、背中に縦の縞模様があるリスです。
一方、今年の夏以降、遺跡の森でエゾリスの姿を見ることも多くなりました。エゾリスはエゾシマリスより一回り体が大きく、おなかが白い以外は暗灰色になっています。何匹かいるらしく、最近は毎日のように見かけます。これほどエゾリスが現れるのは、最近10年間ではなかったことです。どうやらこの秋はドングリなどの木の実が不作で、食べ物を求めて普段行かない場所にもやって来ているようです。確かに遺跡の森で実っているドングリも、昨年より少なめに感じられます。
エゾシマリスは木登りも得意ですが、巣は地面に穴を掘って作ります。毎年11月頃には冬眠に入るようです。エゾリスは木の上に住み、冬でも活動します。どちらも人の姿に気付くと逃げ去ってしまいますが、笹薮に隠れてしまうエゾシマリスに比べると、木の上に逃げるエゾリスは比較的姿を見つけやすいです。「ガシッ、ガシッ」と音を立てて木に登っていくこともあれば、見つからないよう静かに動きを止めていることもあり、気付くと木の上からじっとこちらの様子をうかがっていたりします。紅葉の季節、森の動物にも注目してみてください。(2023年11月)


エゾリスの足跡
雪の季節になると、動物の足跡が雪の上によく見られるようになります。なかなか人前に姿を現さない動物たちでも、足跡からその存在が分かるようになります。遺跡の森で最も普通に見られるのはキタキツネと、ネズミの仲間の足跡です。この冬からは、それにエゾリスの足跡も加わるようになりました。
エゾリスは昨年、何匹か森の中に住みついたらしく、秋まではその姿がよく見られました。冬に入るとほとんど見かけなくなってしまったのですが、足跡があることから元気で暮らしているらしいことが分かります。写真がその足跡です。

この足跡は写真の上方向に進んでいます。飛び跳ねて移動しており、前足を着いた場所より前方に後ろ足が着地しています。従って、4つ1組で逆台形状に並んだ足跡のうち、上の2つが後ろ足、その下のひとまわり小さいのが前足の跡ということになります。足跡をたどった先で、雪を掘り返した穴が見つかることもあります。エゾリスは地中に保存しておいた食料を、雪の上から掘り起こして食べることがあります。ですので、こうした穴は食料を調達した跡かもしれません。
一見すると寂しく見える冬の森ですが、雪の上に注目すると、厳しい寒さの中でもたくましく生きている動物たちの様子が分かります。(2024年2月)



遺跡の森の野鳥~シジュウカラの鳴き声
5月から6月にかけての遺跡の森は、野鳥でにぎやかになります。多くの鳥が繁殖期を迎え、あちこちで鳴き声を響かせています。こうした鳥の中には何種類もの声を使い分けているものもいます。有名なのはシジュウカラで、鳴き声で仲間同士コミュニケーションをとっていることが知られています。鳴き声を文字で表現してもなかなか伝わりづらいのですが、いくつかご紹介してみましょう。平常時、なわばり宣言をするさえずりは「ツピ、ツピ」というものです。これに対し、「ピーツピ」で「警戒しろ」、「ジジジジジ」で「集まれ」という意味があるそうです。「ツピ、ツピ」と鳴いているところに人が近づくと、「ピーツピ」に変わることがよくあります。「ジジジジジ」はエサを見つけたときにも使うようですが、「ピーツピ、ジジジジジ」とつなげた場合は「警戒して集まれ」という意味になり、集まって敵を追い払うときに発せられる声とのことです。
遺跡の森にはシジュウカラに近い種の鳥もいます。特に多いのはハシブトガラで、やはりいろいろな声で鳴き、仲間同士おしゃべりしているように見えることもあります。シジュウカラの「ジジジジジ」に似た鳴き声もあり、やはり「集まれ」と言っているようです。
鳥の鳴き声を覚えておくと、野外を歩くときの楽しみが1つ増えます。遺跡の森のウェブサイトでも、森の中で聞こえる鳥の鳴き声をいくつかご紹介していますので参考にしてみてください。(2024年6月)


赤い実のなる草木~ニシキギの仲間
実りの季節である秋には、様々な草木が実をつけます。紅葉で黄色く色づいた森の中で、特に目につくのは赤い実です。遺跡の森で見られるものだけでも、エゾニワトコ、ユキザサ、コウライテンナンショウ、マイヅルソウなど、赤い実のなる植物にはいろいろあります。
なかでも変わった形の実をつけるのがマユミやオオツリバナなど、ニシキギの仲間(ニシキギ属)の木です。これらは濃い桃色の実を結ぶのですが、熟すと実の下部が割れ、内側の赤い種子が吊り下がって見えるようになります(写真1)。花は初夏に咲くのですが、黄緑色の小さなものであまり目立ちません。実のほうが鮮やかな色で、下向きに咲いた花のように見えます。この赤い種子、野鳥は食べるようですが、じつは毒があり、人が口にするとおなかをこわしてしまいます。そのためなのか、すぐに動物に食べ尽くされてしまうということもなく、実が冬まで残っていたりします。

一方、ニシキギの仲間は材がよくしなり丈夫なため、弓の材料として使われたことが知られています。なかでもマユミの木が良質とされ、そのため「マユミ=真弓」という名前が付けられています。常呂川河口遺跡ではアイヌ文化期の木製の弓が発見されていますが(写真2)、やはりニシキギの仲間が使われていたという調査結果が得られています。食用にはなりませんが、古くから利用されてきた身近な木だったのです。(2024年11月)

「ところ遺跡の森」の関連ページ
| お問い合わせ |
|---|
| 北見市教育委員会社会教育部 ところ遺跡の森 郵便番号:093-0216 住所:北海道北見市常呂町字栄浦371番地 電話:0152-54-3393 FAX:0152-54-3538 |