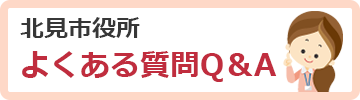MENU
CLOSE
市政執行方針(令和7年3月)

1.はじめに
令和7年第1回定例北見市議会の開会に当たり、新年度の市政執行に対する私の所信を申し上げます。
私が市民の皆さまのご支持を得て、市長の職を担わせていただき、間もなく9年半が経とうとしています。
この間、このふるさと北見が笑顔であふれるよう、全力で市政に取り組んでまいりました。
このような中、昨年2月、私は、このままの財政運営を続けていけば、将来、市の歳出総額が、歳入総額に見合ったものとはならない状況が続き、財政の収支見通しが大幅に悪化するということを中期財政計画の中で、市民の皆さまにお示しをいたしました。
平成18年3月の旧1市3町の合併を経て、新しい北見市となった本市は、これまで、市民の皆さまのご期待に応えられるよう、新しいまちづくりを進めてきたわけでありますが、一方で、全道一大きな面積に加え、全道主要都市の中で最も低い人口密度という環境にあって、道路などの社会インフラや公共施設を多数維持している状況にあり、市の財政は、他都市と比較いたしましても、余力が少ない状況にあったことも事実であります。
昨年11月、市の貯金である基金などで収支不足をやりくりしたり、世代間負担の公平を図るものの、市の借金となる市債などに依存したこれまでの予算編成では、現在進行している人口減少や世界的に発生しているインフレーションに対応した持続可能な財政運営は困難となる見通しを踏まえ、「北見市財政健全化計画」を策定するに至りました。
この計画では、令和7年度から令和9年度までを集中健全化期間とし、事務事業や公共施設の見直しなどを行い、一般会計において令和9年度までに一般財源ベースで単年度約30億円の削減効果額を生み出すとともに、将来の公債費負担を圧縮するため、単年度の市債借入総額を3か年平均で約45億円に抑制するという、未来に向けた、かつてない大規模な財政健全化に取り組むこととしたところであります。
昨年12月に開催した市民説明会におきましては、本当に多くの市民の皆さまからご意見を賜り、このまちの将来について深く思慮いただいていることを痛感したところであり、心から感謝を申し上げます。
本市は、いかなる状況にあっても、市民の皆さまが安心して生活でき、住み続けたいと思っていただける魅力的なまちとして発展し続けていかなければなりません。
そのためにも、早期に安定した財政基盤を確立することが極めて重要であり、財政健全化への不退転の決意と覚悟をもって、取り組んでまいります。
2.市政運営の基本方針
次に、新年度の市政運営の基本的な考え方について申し上げます。
真に必要な市民サービスを提供し、持続可能な市政運営を行うためには、財政健全化を着実に進め、歳入の増加と歳出の削減を同時に図っていかなければなりません。
行政課題などが山積する中で、「北見市財政健全化計画」の初年度となる令和7年度の予算編成は、非常に厳しいものとなりました。
新年度予算については、「北見市財政健全化計画」に沿って既存事業などを見直すことで、計画上の効果額をしっかりと生み出すことを最優先に、政策的な新規事業を制限するなどして、編成したところであります。
本市の財政健全化は、まさに待ったなしでありますが、他方、このまちを、誰もが住みたい、住み続けたくなるまちにするという私の考えは、全く揺るぎなく、委縮したり、立ち止まることはできません。
そのためにも、歳出削減の徹底だけではなく、歳入を増やす方策も併せて検討しながら、持続可能な市政運営に対応できる財政基盤を確立する必要があります。
その一例としては、全庁を挙げて取り組んでまいりましたふるさと納税寄附額が数字を伸ばし、今年度は30億円を超える見込みでありますが、新年度においては、新たに一般財団法人北見振興公社との連携による体制の強化を図り、50億円の寄附額を見込むなど、更に高い目標を掲げ、引き続き、積極的に取り組んでまいります。
今後、更に流動化する社会経済情勢に柔軟に対応し、未来に残していかなければならないものを残し、ふるさと北見の存続と発展を確かなものとすることは、市長である私の最大の責務であります。
私たちは、このまちの将来のため、子どもたち、未来の世代のために、この難局を乗り越えなければなりません。
難局にあるからこそ、将来を見据え、ふるさと北見の未来を切り拓いていくためのビジョンを持つ必要があります。
まさに、令和11年度までの本市が目指すべき姿として今般策定した「第3期北見市地方創生総合戦略」がこれに当たると認識をしており、同戦略に掲げた4つの基本目標である「地域の宝を活用した良質な産業・雇用を創出し、安心して働けるまちを実現する」、「誰もが暮らしやすいまちの魅力を育み、地域へのひとの流れをつくる」、「それぞれの結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり」、「ひとが集い、安全で安心して暮らすことができるまちをつくる」を羅針盤として、取組を進めてまいります。
来るべき令和7年度は、こうした基本的な考え方のもと、知恵を働かせ、創意と工夫をこらし、財政健全化との両立をしっかりと図りながら、「第2期北見市総合計画」に掲げる将来像「ひと・まち・自然きらめく オホーツク中核都市―未来を拓く活力創造都市 北見―」の実現に向け、本市の強みを最大限に活かし、市民の皆さま、さまざまな分野の皆さまとともに、全身全霊を傾けて取り組んでまいります。
3.令和7年度の主要施策
次に、「第2期北見市総合計画」の5つの基本目標に沿い、新年度の主要施策について申し上げます。
(1)健康で安心して暮らせるまちづくり
まず、健康・福祉分野においては、「健康で安心して暮らせるまちづくり」を進めてまいります。
1点目は、「希望あふれる子育て支援の充実」であります。
少子高齢化は本市が直面する最大の課題であり、財政健全化を進めながらも、北見の未来を担う子どもたちに必要な投資を続けていく必要があります。
(子育て支援の充実)
まず、昨年8月から高校生世代の18歳まで助成対象を拡大した子ども医療費助成、そして、昨年4月から開始した第2子以降の保育料一律無償化については、篤志家からのご寄附なども活用しながら、子ども・子育て支援の最重要施策として継続して取り組んでまいります。
また、学校給食費につきましては、1食当たり50円の公費による助成を行うほか、無償化の実現について、国や道に強く働きかけてまいります。
(児童福祉と幼児教育の充実)
次に、児童福祉と幼児教育では、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」について、令和8年度からの本格実施を見据え、新年度から試行的に取り組んでまいります。
また、こども基本法に基づく「こども計画」については、子どもや若者の意見も取り入れた計画を策定いたします。
(青少年の健全育成活動の推進)
次に、青少年の健全な育成に向けては、地域で子どもを見守る子ども食堂の運営について支援するなど、子どもたちが安全で安心して過ごせる多様なニーズに応じた居場所づくりを推進してまいります。
2点目は、「健康に暮らせる保健・医療の充実」であります。
(健康づくり推進体制の充実と健康寿命の延伸)
健康づくりの推進に向けては、保健センターを拠点に、各種保健サービスの提供など、市民の皆さまの生涯を通じた健康をしっかりと支えてまいります。
また、今年度から予防接種法に基づく定期接種に位置づけられた65歳以上の方を対象とした新型コロナウイルスワクチンに加え、本年4月から同様の取扱いとなる帯状疱疹ワクチンについても、市内における接種体制を整えてまいります。
(自ら取り組む健康づくりの促進)
次に、健康づくりの推進に向けては、これまでの総合的ながん対策、中高齢者及び妊娠中の方を対象とした歯周病検診などを推進するほか、「健康づくりポイント」を付与する取組への参加促進などを通じ、市民の皆さまの健康意識の向上と健康寿命の延伸を目指してまいります。
(地域医療の充実)
次に、地域医療では、休日等における市内の歯科診療体制について、北見地域定住自立圏を構成する訓子府町及び置戸町と連携し、これまで日曜日、大型連休中の祝日及び年末年始としていた診療日を大型連休以外の祝日にも拡大して確保してまいります。
また、常呂自治区唯一の病院である常呂厚生病院において、電子カルテシステムなど医療機器等の整備に対して必要な助成を行ってまいります。
3点目は、「支えあう福祉の推進」であります。
(地域福祉活動の促進)
SDGsの理念も踏まえ、北見地域定住自立圏域における障がいのある方の地域生活支援と成年後見制度の普及、利用促進などを通じ、誰もがいきいきと自分らしく暮らし続けることができるやさしい共生社会の実現を目指してまいります。
(高齢者福祉の充実)
次に、高齢者福祉では、高齢者に対するバス料金助成制度について、社会福祉審議会からの答申を踏まえ、持続可能性の視点から、一定のご負担増にご理解をいただきながら、現在のバス乗車証の更新期間をこれまでの3年に1回から1年ごとに見直し、利便性を高めつつ継続をしてまいります。
(障がい者福祉の充実)
次に、障がい者福祉については、引き続き、障がい者就業・生活支援センターなどとも連携し、多様な人材の活躍を推進するため、農福連携などを柱とした障がいのある方の就労支援に取り組むほか、市役所における障がいのある職員の雇用を推進してまいります。
(2)豊かな心と文化を育むまちづくり
2つ目の教育・文化分野においては、「豊かな心と文化を育むまちづくり」を進めてまいります。
1点目は、「豊かな心を育む教育の推進」であります。
(学校教育の充実)
学校教育については、光西中学校において学校施設の長寿命化改修を進め、安全で快適な教育環境を整備してまいります。
また、年々増加している不登校への対策として、新たにデジタル技術を活用した仮想空間、いわゆる「メタバース」に不登校児童生徒の多様な学びの環境を創出してまいります。
さらに、児童生徒1人に1台ずつ整備したタブレット端末及びソフトウエアを更新するなど、国のGIGAスクール構想の着実な推進を通じ、児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな学びを目指してまいります。
(地域との連携による教育の推進)
このほか、本年1月、鈴木直道北海道知事にもご視察をいただきましたが、スポーツ・健康まちづくりの取組の一環として市立学校における本市ならではのカーリング授業を引き続き推進してまいります。
(高校・大学等教育の充実)
次に、高校・大学等教育については、経済的理由により修学困難な生徒及び学生に対する奨学金や入学準備金貸付などを継続してまいります。
また、ふるさと納税を活用した相互協力に関する覚書に基づき、本市に所在する北見工業大学及び日本赤十字北海道看護大学をはじめ、常呂実習施設を有する東京大学への寄附を通じた支援を行うなど、高等教育機関との連携を強めてまいります。
2点目は、「ともに学びあう生涯学習の推進」であります。
(生涯学習の充実)
図書館については、これまで、現在の端野図書館と端野町歴史民俗資料館を機能集約した新たな端野図書館のリニューアルオープンに向けた取組を進めてまいりました。
しかしながら、今般、「北見市財政健全化計画」の集中健全化期間である新年度から令和9年度までの3年間、「第2期北見市総合計画」の実施計画への計上と関連事業費の予算計上を見送ることとし、令和10年度に改めて実施の可否を判断するという決断に至ったところであります。
図書館がまちづくりにおいて大変重要で、不可欠なものであるとの私の認識は、全く変わることはなく、引き続き、中央図書館を核とした図書館サービスを提供してまいります。
(生涯スポーツの推進)
カーリング振興では、地域おこし協力隊のカーリングサポート隊を中心に、市内2つのカーリングホールを活用し、市民利用・観光利用の更なる促進を図ってまいります。
また、子どもの運動意欲向上を目的に平成28年度に開始した多種目体験型スポーツ教室「Jr.アスリートチャレンジアカデミー」などを継続し、誰もがスポーツに親しむことのできる生涯スポーツを振興してまいります。
3点目は、「地域文化を育む文化活動の推進」であります。
(芸術・文化活動の振興)
市民ホールや公民館における音楽や演劇等の公演に加え、北網圏北見文化センターにおける企画展の開催などを通じ、市民の皆さまが質の高い芸術・文化の魅力を楽しんでいただくことができる機会を提供してまいります。
(文化財の保護・継承)
文化財の保護・継承では、ところ遺跡の森において、入口区域と復元竪穴住居の再整備を進めるとともに、国の重要文化財に指定された常呂川河口遺跡墓坑出土品と史跡常呂遺跡を教育・観光資源としても、その魅力を高め、活用してまいります。
(地域間・国際理解の推進)
地域間・国際理解の推進では、国内外の姉妹友好都市などとの関係を深化させてまいりますほか、オホーツク圏活性化期成会や本市と近隣町で形成する北見地域定住自立圏での取組を通じ、オホーツク地域の未来のために地域の課題を的確に捉え、管内市町村との連携をしっかり図ってまいります。
(3)にぎわいと活力あふれるまちづくり
3つ目の産業・観光分野においては、「にぎわいと活力あふれるまちづくり」を進めてまいります。
1点目は、「魅力と活力ある産業振興」であります。
(持続的に発展する農業の振興)
未来へつながる力強い農業の確立に向けては、生産性の向上を図るため、計画的なほ場整備などの土地改良事業を進めるほか、環境負荷低減につながる有機農業の取組などに対する助成に加え、農業生産活動の基盤となる営農用水施設の更新などに取り組んでまいります。
(豊かな林業の推進)
林業では、新年度から森林環境譲与税を活用し、首都圏の移住相談会において本市の林業をPRするほか、本市への移住を検討いただける方や市内林業事業体からの聞き取り調査を行い、有効な就業支援策を検討し、林業の担い手確保につなげてまいります。
また、ゼロカーボンシティの実現に向けた視点のみならず、財政健全化に向けた歳入確保の観点からも、市有林から創出されるJ-クレジットの販売拡大などへの取組を一層強化してまいります。
さらに、新年度から森林環境譲与税を活用し、地域材を活用した住宅の新築や改修費用の一部を助成してまいります。
(活力に満ちた水産業の推進)
水産業では、道が進める水産物供給基盤機能保全事業基本計画に基づき、引き続き、常呂漁港、栄浦漁港の機能保全を図ってまいります。
(地域に根づいた工業の振興)
工業では、IT人材やIT企業誘致の取組である「ふるさとテレワーク」を更に展開させるため、国の地域活性化起業人制度を活用し、首都圏の企業から派遣された人材のノウハウを活かしたプロモーション活動、ワーケーションや二地域居住の推進などを通じ、交流人口の拡大、長期滞在者の増加を図り、当地域への人の流れを創出してまいります。
(活気ある商業活動の促進)
商業では、中心商店街における新規出店支援の内容を見直し、改装費用に対する助成を行うほか、経済団体などと組織する北見市中心市街地活性化協議会と連携し、中心商店街をはじめとするまちのにぎわい創出につなげる取組を進めてまいります。
(地域経済を支える中小企業の振興)
中小企業を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますが、従来の創業促進補助金を融資に対する助成金に改め、創業にチャレンジする方を後押しする支援を行ってまいります。
また、新年度で4年目を迎える北見未来創発プロジェクトについては、デザインをブランドの構築とイノベーションの創出に活用する経営手法、いわゆる「デザイン経営」の普及・啓発を図る取組を進めてまいります。
2点目は、「にぎわいと交流の観光振興」であります。
(着地型観光の推進)
令和8年度から導入する予定の宿泊税については、「北見市観光推進プロジェクト」に基づく本市の持続性の高い着地型観光の実現に資する取組への財源となるものであります。
新年度は、この制度が円滑に導入されるよう、宿泊税の徴収に係る特別徴収義務者となる方に対して、既存のレジシステムの改修や新たなレジシステムの構築等に係る費用を助成するほか、宿泊税の使途についての検討を重ねてまいります。
また、各種SNSを通じ本市の情報を発信する「市民観光アンバサダー」と連携し、発信力強化とイメージ向上を図るほか、観光PRにとどまらない、本市の魅力を市内外へ広く発信するシティ・プロモーションを継続し、交流人口、関係人口、定住人口の拡大に向けた取組を進めてまいります。
(インバウンド対応の推進)
インバウンドについては、観光施設情報の多言語化などの受入環境整備を進め、アジアのみならず各国からのインバウンド機運を更に醸成してまいります。
3点目は、「創造性あふれる雇用環境の充実」であります。
(人材の定着・確保と雇用の促進)
若者の地元への就労促進については、若者就活応援センターのウェブサイトに加え、企業紹介動画や「北見市移住しごとガイドブック」による情報発信を行ってまいります。
また、道と連携し、東京圏からのUJIターンによる就業・起業者及びテレワーク移住者に対する交付金を支給するなど、地域ぐるみで若者人材を確保し、地元企業との雇用マッチングを一層強化してまいります。
(多様な就労環境の創出)
さらに、本市の魅力を積極的に発信し、都市部から本市へのより多くの人の流れを生み出すことに加え、ハラスメントのない職場づくりを推進するなど、働きやすい環境整備を推進してまいります。
(4)自然と調和する安全な住みよいまちづくり
4つ目の環境・生活基盤分野においては、「自然と調和する安全な住みよいまちづくり」を進めてまいります。
1点目は、「豊かな自然環境の保全」であります。
(自然共生と緑豊かな環境の創出)
まず、屯田の杜公園内の親水施設であるウォーターパークと周辺緑地帯の再整備については、先ほど申し上げました新たな端野図書館と一体の整備を行うものでありますので、同様に令和10年度に改めて実施の可否を判断してまいります。
また、野付牛公園については、計画のペースを少し落としながら再整備を進め、自然とふれあえる生活環境を整えてまいります。
(地球環境に配慮した脱炭素・循環型社会の構築)
ゼロカーボンシティの実現に向けては、公共施設における照明のLED化や再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入に対する助成などを行ってまいります。
次に、循環型社会の構築に向けては、3か年計画の最終年度となる廃棄物処理場リサイクルプラザの基幹的整備で、将来にわたる整備費用と温室効果ガス排出量を縮減させるとともに、廃棄物の安定的な処理体制を整えてまいります。
また、食品ロスの削減に向けた取組として、子ども食堂などへの未利用食品を提供する「フードドライブ」を推進してまいります。
2点目は、「快適な生活空間の充実」であります。
(機能的な都市空間の創出)
「北見市都市再生基本構想」における2拠点1軸の1軸として、民間事業者が行っている中央大通沿道地区の第一種市街地再開発事業については、令和8年度に予定されている竣工に向け、円滑な事業遂行のための支援を引き続き行ってまいります。
(道路網の充実)
道路網の充実に向けては、北海道横断自動車道網走線及び遠軽北見道路について、各期成会などを通じた高規格道路網等の整備促進に向けた要望活動などを重ね、事業中区間の整備促進と未事業化区間の早期着手を国や道に強く働きかけてまいります。
また、交通の利便性や安全性の更なる向上のため、緊急性や必要性を勘案しながら、市道の整備を順次進めてまいります。
(公共交通の確保)
次に、公共交通の確保については、人手不足が顕著な路線バスの乗務員の確保に向けて、引き続き、民間企業等受入型の地域おこし協力隊制度を活用した取組を進めてまいります。
また、JR石北本線については、オホーツク圏活性化期成会石北本線部会や市独自の利用促進活動など、維持・存続につながる取組を強めてまいります。
さらに、地域公共交通の現状や課題を踏まえ、「北見市地域公共交通計画」を策定し、持続可能な公共交通の構築に向けた取組を進めてまいります。
(良質な住宅・住環境の形成)
市営住宅については、計画のペースを少し落としながら若葉団地の建替を進めていくほか、既存団地について、外壁などの改修を行い、安全で良質な住環境を整えてまいります。
(水道水の安定供給と下水処理の確保)
次に、上下水道事業については、日々の生活に欠かせないライフラインである水道水の安定的な供給と下水処理による衛生的な住環境維持及び公共用水域の水質保全を図るため、中長期的な視点から、アセットマネジメントの手法による計画的な施設更新を進めてまいります。
3点目は、「地域の安全安心の確保」であります。
私たちはその都度、次なる災害に備えてまいりましたが、昨年は、能登半島における震度7という大きな地震が発生したほか、日向灘を震源とした地震では、本市の姉妹友好都市である高知市、佐川町、大野町を含む1都2府26県707市町村に南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されるなど、改めて、災害の脅威を痛感したところであります。
(防災の強化)
まず、防災・減災の取組としては、防災備蓄機能の強化を図るため、令和8年度の供用開始を目指して、洪水浸水想定区域外における防災備蓄倉庫の整備を進めるほか、常呂自治区において、同報系防災行政無線を更新するなど、暮らしの安全を守るための取組を進めてまいります。
(地域の安全の確保)
次に、地域の安全の確保については、新年度から森林環境譲与税を活用し、倒木による道路の寸断や交通事故の発生を予防するため、市道に隣接している森林の支障木等の伐採を行ってまいります。
また、北見地区消防組合消防本部の消防指令システム及び消防救急デジタル無線を更新するほか、消防車両や消防水利施設を計画的に更新し、消防・救急救命体制の充実を図ってまいります。
(消費者保護の充実)
次に、消費者保護については、身近な窓口である消費生活センターの存在をより多くの方に知っていただくための啓発を行うとともに、手口がますます多様化、巧妙化する悪質商法や特殊詐欺などに対応した相談体制を整え、消費者被害防止に取り組んでまいります。
(5)市民による自主自立のまちづくり
最後に5つ目の地域・自治分野においては、「市民による自主自立のまちづくり」を進めてまいります。
1点目は、「市民主体の住民自治の推進」であります。
(市政への市民参画促進)
市政への市民参画については、「市長への手紙」をはじめ、さまざまな広聴手段によりニーズを把握するとともに、「広報きたみ」や各種SNSを活用し、市政情報を公開することにより、課題を共有してまいります。
また、審議会委員の公募やパブリックコメントなど、政策の意思決定過程に参画できる機会を創出し、市民の皆さまとともにまちづくりを推進してまいります。
(住民自治の推進)
次に、市民主体の協働のまちづくりに向けては、町内会への加入促進に取り組むとともに、住民自治推進交付金制度を通じ、地域コミュニティの活性化を図ってまいります。
また、町内会が行う地域会館整備に対する助成のほか、まちづくりパワー支援補助金により、市民が自ら考え、自ら実践する自主的なまちづくり活動を支援してまいります。
2点目は、「互いに尊重する地域社会の形成」であります。
(多様性を認めあう社会の実現)
男女がともに働きやすく、多様な働き方を選択できるワーク・ライフ・バランスを推進する「きたみワーク・ライフ・バランス認定事業所」の認定に取り組むなど、誰もが性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮し活躍できる社会を実現してまいります。
(人権尊重のまちづくり)
また、本市では、多様な性のあり方や人権が尊重される社会を目指し、令和4年から「パートナーシップ宣誓制度」を、昨年から「ファミリーシップ宣誓制度」を導入いたしました。
これまで、転入転出に伴う負担軽減を図るため、市町村間での連携を広げてまいりましたが、本年4月から北見地域定住自立圏を構成する美幌町、津別町、訓子府町及び置戸町と「ファミリーシップ宣誓制度」を含む連携を開始いたします。
さらに、全ての市民があらゆる差別を受けることなく、LGBTQや障がい者、外国人などを含めた、市民誰もが互いに多様性を認め合い、個人として尊重されるまちをつくるため、本市における人権尊重の基本的な考え方を明確にする「(仮称)北見市人権まちづくり条例」の制定に向けた検討を引き続き進めるほか、人権意識を高揚させるための啓発に取り組んでまいります。
3点目は、「効率的な地域経営の推進」であります。
(行政運営の効率化・適正化)
「北見市財政健全化計画」の初年度となる新年度は、本市の持続可能なまちづくりに向け、大きく舵を切らなければならない1年となります。
他方で、さまざまな社会環境変化などに伴い市民ニーズが多様化、複雑化することにより、更なる増加が見込まれる行政需要に対して、本市においては、従来の手法で応えていくことは極めて困難な状況にあります。
そのため、全庁的な業務内容や課題を可視化する業務量調査の結果を踏まえた、本格的な業務プロセス等の見直し、再構築・集約化を行うとともに、総合支所を含む組織機構の見直しや管理職を含めた職員定数の適正化による総人件費の圧縮にも取り組むなど、行政改革の取組を推進してまいります。
また、歳入確保に向けては、地方創生関係の交付金をはじめとする国や道の政策的予算の積極的活用に加え、ネーミングライツなどの有料広告を拡大するとともに、ふるさと納税のほか、企業版ふるさと納税制度についても寄附の更なる増加に向けたトップセールスなどを進めてまいります。
加えて、令和8年3月に本市が合併20年の節目を迎えることを踏まえ、新年度から2年をかけ、今後の行政運営等のあり方などについて、市民や専門家の皆さまのご意見も伺いながら、検討を行ってまいります。
(行政サービスの向上)
行政サービスの向上については、新たに電子調達システムを導入し、入札参加者が市役所に来庁せずとも、オンライン上での入札等を可能とすることで、入札参加者の負担軽減と利便性向上を図ってまいります。
4.むすび
以上、令和7年度の市政運営の基本的な考え方と主要施策について申し上げました。
財政健全化とは、今後見込まれる収支不足を解消するのみならず、将来への新たな投資余力を持てる健全な財政運営が可能となるように体質そのものを改善することであります。
「二兎を追うものは一兎をも得ず」ということわざがありますが、本市のこれまでの歴史において諸先輩方がそうされてきたように、ピンチをチャンスに変えるためには、「財政健全化」と「ふるさと北見の発展」の二兎を追い求めることが必要であります。
私は「二兎を追うものだけが二兎を得る」の精神で、決して諦めず、前例のない改革などを躊躇なく前に進め、この難局を乗り越えてまいる所存であり、私の公約につきましても、財政健全化との両立を図りながら、今後におきましても任期の中で実現をするべく、取り組んでまいります。
市民の皆さま、議員の皆さまのご支援とご協力を引き続き賜りますよう、心からお願い申し上げ、新年度の市政執行方針といたします。
| お問い合わせ |
|---|
| 企画財政部市長政策室政策課 電話:0157-25-1101 |
このページについてのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。