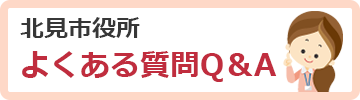MENU
CLOSE
続縄文時代前半の土器
約1000年間にわたって続いた続縄文時代は、土器の型式の変化に基づいて、大きくは前半(紀元前4世紀~紀元1世紀ころ)と後半(紀元2~6世紀ころ)の2つに分けられています。
さらに細かい時期区分については様々な考え方がありますが、ここでは前半を早期・前期・中期、後半を後期・晩期に分割する説に従ってご紹介します。
続縄文時代前半は、北海道各地で地域色のある型式の土器が作られた時代です。オホーツク海沿岸地域では続縄文時代前期から中期にかけて、宇津内(うつない)IIa式・宇津内IIb式と呼ばれる土器が作られていました。これに混じって、隣接する地域の型式の土器も見つかっています。
続縄文時代早期の土器
紀元前4~3世紀ころに相当します。続縄文時代の初めころの遺跡は数が少なく、土器の変化も詳しく分かっていない部分があります。

■ 常呂川河口遺跡・329b号土坑出土 ■ 後列中央の土器の高さ:約14cm
■ 縄文時代晩期後半 ■ 紀元前4世紀頃
墓におさめられていた土器のセットです。縄文時代晩期末から続縄文時代初頭のものと考えられ、底部は幣舞式の特徴である曲面ではなく、平面か、やや上げ底になっています。口が2つある「双口土器(そうこうどき)」(後列右)のような特殊な形の土器も含まれ、また高さ5cm前後の小型土器が10個まとまっていました。

■ 常呂川河口遺跡出土 ■ 残存部の高さ:約29cm(底部欠)
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前4世紀頃
続縄文時代初頭の深鉢形土器。上部にある「⊃⊂」のような形の文様が「変形工字文」と呼ばれる文様です。東北地方の縄文時代晩期の土器に見られる「工字文」という文様が変化して取り入れられたものと考えられています。

■ 常呂川河口遺跡出土 ■ 残存部の高さ:約24cm
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前4世紀頃
続縄文時代初頭の深鉢形土器。上部にある曲線の文様は「変形工字文」からのアレンジで現れた文様と考えられています。

■ 常呂川河口遺跡出土 ■ 高さ:約29cm
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前4世紀頃
続縄文時代初頭の深鉢形土器。この土器の上部にある波形の曲線の文様も、「変形工字文」からのアレンジで現れた文様と考えられています。

■ 常呂川河口遺跡・157a号竪穴住居跡出土 ■ 高さ:約41cm
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前3世紀頃
上に紹介した続縄文時代初頭の土器に続いて、オホーツク海沿岸地域で作られていた土器で、型式名は美幌町・元町2遺跡に由来します。
この時期から、口の部分をめぐるかたちで、小さな丸い瘤(こぶ)のような出っ張りの文様が現れます。この瘤形の文様は棒で内側から突いて付けたもので、突瘤文(つきこぶもん)と呼ばれています。

■ 常呂川河口遺跡・121号土坑出土 ■ 高さ:約9cm
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前3世紀頃
小型の壷形土器で、墓に副葬されたものと考えられるものです。
元町2式土器では、この土器のように突瘤文が2段めぐらしてある場合があります。

■ 常呂川河口遺跡・547a号土坑出土 ■ 高さ:約45cm
■ 続縄文時代早期 ■ 紀元前3世紀頃
続縄文時代早期の釧路地方を中心に作られていた型式の土器。
続縄文時代前期の土器
紀元前2~1世紀ころに相当します。オホーツク海沿岸地域では宇津内IIa式土器と呼ばれる型式の土器が作られました。

■ 栄浦第二遺跡・87号土坑出土 ■ 高さ:約11cm
■ 続縄文時代前期 ■ 紀元前2~1世紀頃
宇津内IIa式土器の小型の完形土器。「宇津内」は斜里町の遺跡名からとられています。この土器は墓の副葬品として埋められていたものです。

■ 栄浦第二遺跡・87号土坑出土 ■ 高さ:約11cm
■ 続縄文時代前期 ■ 紀元前2~1世紀頃
上の土器と一緒に埋められていた宇津内IIa式土器の小型の完形土器。宇津内IIa式土器に付けられる突瘤文は1段のみになります。

■ 栄浦第二遺跡・84a号土坑出土 ■ 高さ:約38cm
■ 続縄文時代前期 ■ 紀元前2~1世紀頃
宇津内IIa式土器の大型の甕形土器。穴の中に埋められた「埋甕」の状態で発見されましたが、土器の中に何が入っていたかは分かっていません。
続縄文時代中期の土器
紀元前1~紀元1世紀ころに相当します。オホーツク海沿岸地域では宇津内IIb式土器と呼ばれる型式の土器が作られました。

■ 常呂川河口遺跡・459号土坑出土 ■ 高さ:約40cm
■ 続縄文時代中期 ■ 紀元前1~紀元1世紀頃
宇津内IIb式土器の深鉢形土器。上部に2つ穴のあいた取っ手のような出っ張りが4つあります。この取っ手とその下の文様を合わせて見ると、フクロウの顔を表現しているようにも見える、特徴的なデザインの土器です。

■ 常呂川河口遺跡・83c号竪穴出土 ■ 高さ:約13cm
■ 続縄文時代中期 ■ 紀元前1~紀元1世紀頃
続縄文時代中期の北海道東部・釧路地方を中心に作られていた型式の土器。続縄文時代前期に釧路地方で作られていた下田ノ沢I式土器はこの地域では見つかっていません。従って、続縄文時代中期になって人や物の交流が活発化し、釧路地方の土器の分布が拡大したことを示すものと考えられています。
「ところ遺跡の森」の関連ページ
| お問い合わせ |
|---|
| 北見市教育委員会社会教育部 ところ遺跡の森 郵便番号:093-0216 住所:北海道北見市常呂町字栄浦371番地 電話:0152-54-3393 FAX:0152-54-3538 |
お問い合わせは下記フォームをご利用ください
行政・まちづくり
地域・まちづくり
自治区
まちづくり協議会
まちづくりパワー支援補助金
地域・まちづくり
北見市誕生のあゆみ
北見市誕生のあゆみ
情報政策
情報化に関すること
行政評価
行政評価
行財政改革・DX
財政
財政資料
使用料等検討委員会
財政健全化
条例・規則
各種条例・規則
その他
人事・採用
正規職員
会計年度任用職員
- 令和8年度会計年度任用職員の募集(子ども未来部保育施設課)
- 令和8年度会計年度任用職員の募集(子ども未来部青少年課・児童館会計年度職員)
- 令和8年度 会計年度任用職員(公営住宅管理人)の募集(公営住宅管理課)
- 令和8年度会計年度任用職員を募集します(市民環境部戸籍住民課)
- 令和8年度会計年度任用職員(窓口事務員)の募集(仁頃出張所)
- 令和8年度会計年度任用職員(窓口事務員)の募集(相内支所)
- 令和7年度会計年度任用職員の募集(やすらぎ苑)
- 令和8年度市民活動課・留辺蘂市民環境課会計年度任用職員(交通安全推進員)の募集
- 令和8年度 会計年度任用職員(温根湯温泉支所窓口事務員)の募集
- 会計年度任用職員を募集します(子ども未来部 子ども総合支援センター)
- 令和7年度会計年度任用職員(給食調理補助員)の募集(学校教育部学校給食課)
- 会計年度任用職員(給食調理補助員代替)の募集(学校教育部学校給食課)
- 「登録」による会計年度任用職員採用候補者の募集
その他
ハラスメント事案への市の対応に関する第三者調査委員会
計画
政策
定住自立圏
防災
まちづくり
都市計画・住宅・土地
環境
廃棄物
健康福祉
子ども・子育て
商業労政
観光
教育
その他
連携協定・連携事業
連携協定・連携事業
まちづくり
統計
ポケット統計
統計書
調査関連
その他
施設
住民センター
生涯学習施設
北見の施設
端野の施設
常呂の施設
留辺蘂の施設
- 大和地区住民センターの使用料改定(令和7年10月1日から)
- 温根湯温泉多目的センターの使用料改定(令和7年10月1日から)
- 温根湯温泉福祉センターの使用料改定(令和7年10月1日から)
- 留辺蘂西区住民センターの利用料金改定(令和7年10月1日から)
- 留辺蘂住民交流センターの利用料金改定(令和7年10月1日から)
- 瑞穂地区農村環境改善センターの使用料改定(令和7年10月1日から)
- 北見市はあとふるプラザ
- 温根湯温泉福祉センター
- 大和地区住民センター
- おんねゆ温泉花公園施設
- 留辺蘂西区住民センター
- 留辺蘂町公民館
- 留辺蘂町下水道管理センター
- 留辺蘂図書館
- 留辺蘂児童館
- 温根湯温泉フレンドセンター
- 北見市留辺蘂学校給食センター
- 金華浄水場・温根湯温泉浄水場・大和浄水場・瑞穂浄水場
- 留辺蘂住民交流センター
- 留辺蘂自治区地域住民のスポーツ熱を支えるスポーツゾーン
- 瑞穂地区農村環境改善センター
- 留辺蘂総合支所アクセス
- 留辺蘂自治区社会体育施設
- 八方台森林公園(ぱるむ・キャンプ場)
- 留辺蘂町リサイクルセンター
- 富岡最終処分場(北見市[留辺蘂自治区]・訓子府町・置戸町一般廃棄物最終処分場)
- 滝の湯ふれあいの里(足湯)
北見のスポーツ施設
端野のスポーツ施設
常呂のスポーツ施設
留辺蘂のスポーツ施設
その他
入札・契約
トピックス
登録申請など
入札予定・結果
- 入札結果(令和8年1月執行)
- 入札結果(令和7年12月執行)
- 入札結果(令和7年11月執行)
- 入札結果(令和7年10月執行)
- 入札結果(令和7年9月執行)
- 入札結果(令和7年8月執行)
- 入札結果(令和7年7月執行)
- 入札結果(令和7年6月執行)
- 入札結果(令和7年5月執行)
- 北見市の水道事業における単価表の公表
- 入札結果(令和7年4月執行)
- 入札結果(令和7年度)
- 地域限定型一般競争入札予定情報(令和7年度)
- 建設工事発注予定情報(R8.2現在)
- 北見市土木工事見積策定単価の公表について
- 入札結果(令和7年2月執行)
- 入札結果(令和7年1月執行)
- 入札結果(令和6年12月執行)
- 入札結果(令和6年11月執行)
- 地域限定型一般競争入札予定情報(令和6年度)
- 入札結果(令和6年10月執行)
- 入札結果(令和6年9月執行)
- 入札結果(令和6年8月執行)
- 入札結果(令和6年7月執行)
- 入札結果(令和6年6月執行)
- 入札結果(令和6年5月執行)
- 入札結果(令和6年4月執行)
- 入札結果(令和6年度)
- 一般競争入札予定情報(令和5年度)物品供給等
- 地域限定型一般競争入札予定情報(令和5年度)
- 一般競争入札予定情報(令和5年度)
- 入札結果(令和5年度)
- 地域限定型一般競争入札予定情報(令和4年度)
- 入札結果(令和4年度)
- 建設工事発注予定情報(R3→R4繰越分)
- 北見市入札結果
入札契約制度
- 予定価格の事後公表の試行
- 北見市の市有施設に係る電力調達の入札導入方針
- 談合等不正行為の対応
- 建築士法改正に伴う設計業務および工事監理業務の契約手続きの取扱い
- 北見市の公契約に関する指針
- フレックス工期契約工事に関する届出
- 週休2日工事の実施について(令和7年4月1日更新)
- 北見市入札契約制度
- 低入札価格調査制度および最低制限価格制度の基準改正
- 単品スライド条項の運用改定について
- 配置予定技術者の事前確認事務処理要領の基準改正
- 現場代理人の兼任に関する取扱要領の基準改正
- 契約約款の改正(R5.4.1)
- 公共工事中間前金払制度に関する届出
- 契約約款の改正(R2.10.1)
- 契約約款の改正(R2.4.1)
契約関係書式
- 市有地貸付のご案内
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R7.9.17告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.9.17告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.9.9告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.9.9告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.8.19告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R7.8.5告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R7.8.5告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R7.8.5告示
- 建設工事等情報(市長部局 電気)R7.7.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R7.7.1告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R7.7.1告示
- 建設工事等情報(市長部局 造園)R7.5.27告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R7.5.20告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.5.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.5.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.4.22告示
- 建設工事等情報(市長部局 電気)R7.4.15告示
- 建設工事等情報(市長部局 建設)R7.4.15告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 電気)R7.4.8告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R7.4.8告示
- 入札契約関係の届出・様式
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.3.31告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R7.3.31告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R6.10.29告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R6.8.27告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R6.8.27告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R6.8.20告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.7.23告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R6.7.23告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R6.7.23告示
- 建設工事等情報(市長部局 電気)R6.7.17告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R6.7.9告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R6.7.2告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.7.2告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R6.7.2告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R6.7.2告示
- 建設工事等情報(上下水道局 一般土木)R6.6.25告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.6.25告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.6.18告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.5.28告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R6.5.28告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R6.5.28告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.5.28告示
- 建設工事等情報(市長部局 管)R6.5.14告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R6.5.14告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.4.23告示
- 建設工事等情報(市長部局 電気)R6.4.16告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R6.4.9告示
- 建設工事等情報(上下水道局 水道施設)R6.4.9告示
- 建設工事等情報(市長部局 建築)R6.4.9告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.4.2告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.3.26告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R6.3.26告示
- 各種契約約款
- 建設工事等情報(市長部局 機械器具設置)R5.6.27告示
- 建設工事等情報(市長部局 一般土木)R5.4.4告示
公募
その他
工事検査
市議会
本会議
ようこそ市議会へ
市議会とは
議員紹介
傍聴・陳情など
会議録
議会広報・出版物
データライブラリ
行政視察
インターネット中継
情報公開
情報公開
個人情報保護
申請・届出
手続きの際の本人確認
新型コロナウイルス関連
住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバー
税金
水道・下水道
環境保全
ペット
墓地・霊園
- 使用料(維持料)の返還を受けるための届出(還付請求書)
- 維持料の免除を受けるための届出(減免申請書)
- お墓の建立場所を返還するときの届出(返還届)
- 親族外の方のお骨を埋蔵・収蔵・改葬するときの届出(親族外埋蔵等承認申請書)
- 納骨されたお骨を移動するときの届出(改葬許可申請書・承諾書)
- 埋蔵・収蔵されている証明を受ける届出(埋蔵等証明願・承諾書)
- 墓地・霊園に納骨するときの届出(埋蔵等届)
- お墓の使用者を変更するときの届出(承継使用許可申請書)
- 使用者が代理人を廃止するときの届出(代理人廃止届)
- 市外の使用者が代理人を付けるための届出(代理人届)
- 使用者の住所や氏名が変更となったときの届出(記載事項変更届)
- 使用許可証の再交付を受けるための届出(再交付申請書)
- 墓地・霊園を使用するときの届出(使用許可申請書)
- お墓を建立・改築・撤去等をするときの届出(工事関係届出)
公営住宅
建築・建設・工事
道路・河川
公園・緑地
都市計画・都市景観
福祉
- 医療費助成の資格・給付、養育医療の資格に関する申請様式
- 国民健康保険の資格に関する申請様式
- 介護サービス事業者の業務管理体制の整備
- 介護保険事業等に係る事故報告
- 【介護保険事業所の方向け】訪問介護の回数が多いケアプランにかかる届出
- 【介護保険事業所の方向け】軽減法人による利用者負担軽減実施にかかる申出
- 【介護保険事業所の方向け】軽度者の方に対する福祉用具貸与のための確認
- 介護保険の被保険者証などの再交付申請
- 【介護保険事業所の方向け】住宅改修理由書作成料の請求
- 【介護保険事業所の方向け】介護保険受領委任払い用の各種様式
- 【介護保険事業所の方向け】介護報酬請求事務における過誤申立
- 北見市高齢者福祉サービスの申請に関する様式
- 地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援事業者の指定申請・更新申請・変更の届出
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請・更新申請・変更の届出
- 介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届等に関する届出書
- 特定事業所集中減算の届出
- 通所介護事業所における夜間宿泊サービスの届出
- 国民健康保険の第三者行為に関する届出様式
- 国民健康保険の給付に関する申請様式
- 地域包括支援センターの設置・変更等の届出
- 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務の一部委託
- 社会福祉法人に係る各種申請等
- 現況報告書等の届出
医療・健診
農林業
産業・商工
教育・文化
スポーツ
行政・まちづくり
防災
その他
監査
ご意見募集(パブリックコメント)
- 北見市学校教育推進計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果
- 北見市こども・若者計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果
- 「第3期北見市スポーツ推進計画(案)」に対するパブリックコメントの実施結果
- 「第4次北見市社会教育計画(案)」に対するパブリックコメントの実施結果
- 第2次北見市立図書館振興計画(案)に対するパブリックコメント実施結果について
- 北見市地域防災計画(案)及び北見市水防計画(案)に対するパブリックコメント実施結果
- 北見市新型インフルエンザ等対策行動計画(素案)に対するパブリックコメント実施結果
- 北見市地域公共交通計画(案)に対するパブリックコメント実施結果
- 北見市過疎地域持続的発展市町村計画(案)に対するパブリックコメントの実施結果
- 【募集終了】第12次北見市交通安全計画(案)に対するパブリックコメント
- 【募集終了】北見市地域防災計画(案)及び北見市水防計画(案)に関する意見公募を実施します
- 「多様性を認め合うまち北見市人権条例(素案)」に対するパブリックコメント実施結果
- 北見市強靱化計画(案)に対するパブリックコメント実施結果
ご意見募集案件
広聴
市民相談
オンブズマン
広報・広聴モニター
道路・河川
私道・市道・河川
その他
地域交通
公共交通への取り組み
北見市営バス
その他
広告事業
広告事業
地域力の創造
地域おこし協力隊