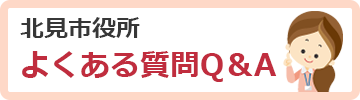MENU
CLOSE
Q&A国民健康保険(国保)のよくある質問
加入や喪失に関すること
Q1 職場の健康保険に加入したのですが、国保はどうしたらいいですか?
職場の健康保険に加入しても、自動的には国保の脱退とはなりません。
国保を脱退するための届出が必要です。届出をしないと国保に加入し続けることになり、保険料を請求されますので届出は忘れずにお願いします。
【届出に必要なもの】
- 職場の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(※1)
- 国民健康保険の「資格確認書(※2)」
- 本人確認ができる書類(有効期間があるものは、有効期間内のもの)
- 世帯主および脱退する方のマイナンバーが確認できるもの
(※1)職場から未交付のときは加入したことを証明するもの
(※2)マイナ保険証をお持ちの方は、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です
Q2 職場の健康保険に加入後、国保の資格で受診した場合どうすればいいですか?
国保での医療給付分(医療費の7~8割)をお返しいただくことになりますが、所定の「同意書」等を提出していただいた場合は、国保と職場の健康保険の間で精算できます(これを「保険者間調整」といいます)。
所定の「同意書」等は脱退の届出の際に提出いただけますので、該当の場合はご連絡くださいますようお願いします。
ただし、全ての医療費を精算できない場合や、職場の健康保険の都合により保険者間調整ができない場合は、改めて医療費の返還をお願いすることがありますので、ご了承ください。医療費の返還が発生する場合は、別途通知いたします。なお、返還相当額は、申請により職場の健康保険から支払われます。
Q3 資格確認書(もしくは資格情報のお知らせ)をなくしてしまいました。再発行できますか?
資格確認書および資格情報のお知らせを紛失された方は、申請により再交付を受けることができます。
下記【申請に必要なもの】をお持ちいただき、国保医療課または支所、出張所、総合支所で再交付の申請をしてください。
なお、資格確認書の再交付を希望される方でマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナ保険証を登録しご使用いただくことで、資格確認書の再交付を受けることなく、医療機関等に受診できます。
また、診療情報に基づいたより良い医療を受けられるなどさまざまなメリットがありますので、ぜひ、保険証利用登録を行ってください。
【申請に必要なもの】
申請により交付する「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」は通常、窓口でお渡しとしますが、本人確認ができない場合や、同じ世帯の方以外の方が申請された場合は、後日郵送にて、お渡しすることとなります。
Q4 今月から職場の健康保険に加入しました。今月末期限の保険料は払わなくていいですか?
国保は、4月から3月までの12か月分を6月末から3月末までの10回の納期に分けて納めていただきます。
そのため、1回あたりのお支払額は1.2か月分相当になり、各月末の納期限の保険料額が各月の保険料額に対応しているわけではありません。
従って、国保を脱退する手続きをしていただいた翌月に精算することになりますので今月末期限の保険料は、いったん納めていただき、納め過ぎとなった場合はお返しすることになります。なお、脱退手続きの際に精算された場合は納める必要はありません。
保険料に関すること
Q5 保険料が上がったのはどうしてですか?
保険料が上がる理由として以下A(1)~A(9)のようなことが考えられます。
A(1) 料率が前年度より上がっている場合、所得が変わらなくても保険料は上がります。
「保険料の料率」は、3月の市議会において議決され、決定しています。詳しくは、「保険料の計算方法」のページに掲載しています。
A(2) 前年度中の所得が増えると保険料は上がります。
保険料の計算には、前年中の1月1日~12月31日までの所得を用いており、国保に加入している方それぞれの所得から所得割算定基礎額を求め、その額の世帯合計に所得割の料率を乗じて算出します。そのため、前年中の所得が増えると保険料も上がります。
A(3) 世帯に所得の未申告の方がいる場合、保険料が上がることがあります。
国保には、所得が一定基準を下回る世帯に対して減額制度がありますが、世帯主および国保に加入している方の中で未申告の方がおりますと、世帯の所得 を把握することができないため、実際には世帯の所得が低くても保険料の減額を適用することができません。
該当となる方は、市民税課または総合支所総務課で申告してください。
A(4) 前年度に比べ、今年度の減額割合が下がる場合、保険料は上がります。
世帯の人数や総所得が前年と変わると減額割合が変わることがありますが、減額割合の変更より、減額する額が少なくなることで保険料は上がります。
- 減額割合の変更によるもの(7割→5割、7割→2割など)
- 減額対象外によるもの(7割→減額なし、2割→減額なし など)
A(5) 非自発的失業者に係る保険料の軽減(特例軽減)の対象期間が終了している方は保険料は上がります。
特例軽減は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
詳しくは国保医療課までお問い合わせください。
A(6)世帯に国保加入の方が増えると保険料は上がります。
国保には、協会けんぽ等のような被扶養者の考え方はないため、世帯に国保加入者が増えると、被保険者一人当りを単位として負担していただく均等割額や所得のある方には所得割額が加算されるため、その分の保険料が上がります。
A(7) 被保険者に今年度40歳になられる方がいる場合、介護分の保険料が含まれるため保険料は上がります。
40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の保険料には、介護分の保険料が含まれるため、その分の保険料が上がります。
そのため、今年度40歳になられる方の生年月日が4月2日~6月1日の方には、介護分の保険料を新年度当初(6月)の通知書に含めて通知します。
なお、今年度40歳になられる方の生年月日が6月2日以降の方には、誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から介護分の保険料が生じ、誕生月の 翌月(1日生まれの方は、誕生月)に通知します。
A(8) 世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、保険料が上がることがあります。
国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は医療分と支援金分保険料の平等割額が半額となりますが、その後3年間は平等割額が4分の1減額となり、軽減額が少なくなるため保険料が上がります。
A(9) 被保険者に今年度より小学生となったお子様がいる場合、保険料は上がります。
未就学児の均等割は2分の1が軽減されますが、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過すると軽減がされなくなるため、保険料が上がります。
Q6 国保以外の健康保険に加入しているのになぜ保険料を払わなくてはならないのですか?
国保の各種届出や保険料を納める義務は、世帯主にあります。
従って、世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合でも世帯の中に国保の加入者がいる場合は、これらの義務を負うことになります。
この場合の世帯主のことを「擬制世帯主」と言います。
ただし、申請により、国保上の世帯主を変更することができますが、現在の擬制世帯主が「世帯主変更に同意していること」、「擬制世帯主に代わり申請者が国保上の世帯主になることを希望していること」、「保険料の未納がないこと」などの条件があります。
Q7 保険料が年金から引き去り(特別徴収)されていますが、口座振替や納付書払いにはできないですか?
年金引き去り(特別徴収)されている方については、申し出により、口座振替への変更はできますが、納付書で納めることは認められておりません。
なお、保険料の納付額は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除は、保険料を納付された方が適用を受けられます。
年金引き去りになる方の保険料をご本人以外の方の社会保険料控除として適用を希望する場合は、適用を希望する方の名義で口座振替をご選択ください。
| お問い合わせ |
|---|
| 国保医療課 電話:0157-25-1130 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
くらし
戸籍・住民票・印鑑登録
住民異動届・住民票
印鑑登録
戸籍
住民基本台帳ネットワークシステム
特別永住者証明書
自動車の臨時運行
その他
- 10月1日から証明書の手数料が変わります
- 町名変更・住居表示実施後の住所変更
- 令和7年度指定納付受託者の指定について
- 手数料などのお支払いでキャッシュレス決済が利用できます
- 「かんたん証明申請」をスタートしました
- 市役所での手続きをわかりやすく!「手続きチェックシート」を導入しました
- 窓口封筒をご利用ください
- メモリアルフォトコーナーで記念撮影はいかがですか
- 北見市最新人口統計
- 北見市役所の窓口サービス改善の取り組み経過
- 手続きの際の本人確認とマイナンバーの確認にご協力ください
- 戸籍住民課関連手数料・使用料一覧
- 窓口手続きの簡略化と統一化の取り組みについて(ワンストップサービス推進事業)
- パスポートの本人確認書類
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
- 住民票・印鑑証明の電話予約による時間外交付サービス
税
市道民税
- 令和8年度(令和7年分)市・道民税の申告
- 10月1日からコンビニ交付の手数料が変わります
- 住宅借入金等特別税額控除の延長
- 配偶者控除および配偶者特別控除の見直し
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告
- 法人市民税法人税割の税率改正
- 個人住民税(市・道民税)の住宅借入金等特別税額控除
- 市・道民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
- 給与所得控除の見直し
- 所得割の税率・税額控除
- 個人住民税(市・道民税)の寄附金税額控除
- 令和6年度個人住民税(市民税・道民税)の定額減税について
- 市民税・道民税・森林環境税 特別徴収の手引き
- 公的年金等(雑所得)に対する特別徴収【年金引き去り】の実施
- 異動届出書の書き方
- 退職所得に係る市民税・道民税の特別徴収
- 所得の種類と所得金額の計算方法
- 個人住民税とは
- 令和3(2021)年度以降の個人市民税・道民税の改正
- 市民税・道民税の非課税措置の見直し
- これまでの税制改正
その他市税
各種証明書
固定資産とは
固定資産税の証明・お問い合わせなど
納税
申請様式
猶予・免除・軽減等の措置
小学生の税の書道
年金
国保・後期高齢者医療
国民健康保険
国民健康保険料
給付
後期高齢者医療制度
健康診断
医療費助成制度等
水道・下水道
経営・事業計画
料金のご案内
各種お手続き
上下水道局案内
災害への備え
水道
下水道
断水・濁水情報
お客様へ
- 漏水を発見したときは
- マンホール周辺の舗装が破損しています
- 冬期マンホールの段差にご注意ください
- 水が出ないときは
- 悪質な訪問販売などにご注意を!
- 漏水調査をかたる不審な電話にご注意を!
- 北見市上下水道事業等の業務に係る公金の収納事務の一部委託の公表
- スマートフォンアプリ決済による水道料金・下水道使用料のお支払い
- 長時間使用を停止した場合の適正な貯水槽水道(受水槽)の衛生管理
- 貯水槽の管理
- 水道料金・下水道使用料の簡易計算
- 上下水道料金のお支払い相談等のご案内
- 上下水道料金のご案内
- 水道料金等収納証明書交付申請
- 遅延損害金及び延滞金
- 下水道事業受益者負担金及び分担金のお支払い
- 水道料金・下水道使用料のお支払い
- 「重要 水道料金・下水道使用料 納入通知書」が届いたお客さまは二重払いにご注意ください。
- 下水道使用料の減免制度
- 水道メーターの取替にご協力をお願いします
- 家の中での漏水発見
- 水道料金が高い(水量が多い)と感じられた場合
- 使用者名義や使用用途等の変更の届出
- 水道料金・下水道使用料の計算方法
- 水道の使用を開始されるお客様へ(定型約款のご案内)
- 北見市指定上下水道工事事業者
- トイレを水洗化されていないお客様へ
- 中高層集合住宅にお住まいの方は停電で水が止まる場合があります
- ディスポーザの設置
- 下水道に流してはいけないもの
- 水道管の凍結を防ぐために
- 下水道事業受益者負担金および分担金制度
- ご家庭の水道管は誰のもの?
- 大雨時の排水不良
- 下水道マンホールや公共汚水ますの異常を発見したときは
- 北見市のマンホールカード
事業者の方へ
- 給排水装置関係書類の図面交付等
- 事業場排水の水質規制
- 北見市の水道事業における単価表の公表
- 水道施設等の付近で工事を行う際は
- 給水装置工事設計施工指針
- 北見市上下水道局のインボイス制度への対応
- 行政財産の目的外使用申請(上下水道局)
- 排水設備工事設計施工指針
- 給排水装置工事関係書類の様式
- 上下水道事業に係る手数料(令和7年10月1日改定)
- 下水道(汚水)使用量の減量認定制度
- 北見市上下水道工事事業者の申請(上下水道局)
- 建設工事等における下水道への臨時排水
- 開発行為等に伴う公共下水道設置
- 下水道への雨水接続および雨水流出抑制
- 排水設備工事責任技術者試験
- 専用水道
- 下水排除基準
- 北見市の下水道事業における単価表の公表
- 水道工事 仕様書
- 下水道事業に関するPPP/PFI提案窓口
- 下水道工事 仕様書・標準図 (管渠編)
イベント
環境・ゼロカーボン
環境への取り組み
環境教育
環境計画・審議会
環境保全
調査
井戸水・浄化槽
地球温暖化対策・ゼロカーボン
再エネ・省エネ・新エネ
脱炭素関連補助金
その他
動物
ペット
動物病院
野生動物
ゴミ・リサイクル
計画・制度
ごみの分別
ごみの減量・リサイクルに関すること
事業系ごみの出し方
不法投棄
高齢者等ごみ出し支援
ごみ処理施設
手数料
し尿
その他のごみに関すること
- 資源ごみ及び容器包装の売払い等による収入とその使途の状況
- 指定ごみ袋の価格改定に伴うお知らせ
- クリーンライフセンターでのごみ処理中に、リチウムイオン電池の発火・発熱が多発しています!!
- 焼却炉に混入した焼却不適ごみ
- ペットボトルの分別
- 令和7年度クリーンライフセンター発火監視システムの作動状況
- 北見市指定ごみ袋・ごみ処理券の景品利用の禁止について
- 清掃ボランティアごみ
- その他のごみに関すること
- ロコ・ソラーレ10周年記念コラボマーク「ロコ・エコ」
- ご家庭で使用されたマスク・簡易検査キット等の捨て方に関するお願い
- マスコットキャラクター エコロン
- ごみステーション管理
- 廃棄物の野焼き禁止
- 【重要】注射針は家庭ごみとして出さないでください
- 北見市ごみ分別アプリ
公営住宅
公営住宅
計画
住宅審議会
その他
子育て
相談窓口
保育園・保育所
子育て相談センター
特別保育
児童センター・児童クラブ
手当・助成
制度・事業
会議・計画
情報発信
その他
消費生活
消費生活相談窓口
物価情報
その他
男女共同参画
男女共同参画プランきたみ
男女共同参画審議会
関連情報
ワーク・ライフ・バランス
人権
交通安全
交通安全
チャイルドシート
市民活動・市民協働
市民協働のまちづくり
町内会
住民センター
- 【端野自治区】北見市地域生活センターの使用料改定について
- 北見自治区住民センターの利用料金改定(令和7年10月1日から)
- 留辺蘂西区住民センターの利用料金改定(令和7年10月1日から)
- 留辺蘂住民交流センターの利用料金改定(令和7年10月1日から)
- 令和7年10月1日から常呂自治区住民センターの使用料を改定します
- 瑞穂地区農村環境改善センターの使用料改定(令和7年10月1日から)
- 留辺蘂西区住民センター
- 東相内地区住民センター
- 相内地区住民センター
- 西相内多目的地域会館
- 大正住民センター
- 豊田住民センター
- 仁頃住民センター
- 川東住民センター
- 上ところ住民センター
- 上仁頃住民センター
- 小泉住民センター
- 西地区住民センター
- 住民センター一覧
- 上ところコミュニティプラザ
- 北地区住民センター
- 南地区住民センター
- 高栄地区住民センター
- 常盤地区住民センター
- 北光地区住民センター
- 中央地区住民センター
- 緑地区住民センター
- 東地区住民センター
- 美山地区住民センター
- 留辺蘂住民交流センター
- 瑞穂地区農村環境改善センター
安全安心の地域づくり推進協議会
北見市民憲章・都市宣言
その他
霊園・墓地
選挙
選挙のお知らせ
各選挙の結果
- 第27回参議院議員通常選挙の結果(令和7年7月20日執行)
- 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果
- 北見市長選挙の結果(令和5年9月10日執行)
- 北海道知事選挙の結果(令和5年4月9日執行)
- 第26回参議院議員通常選挙の結果(令和4年7月10日執行)
- 北見市議会議員選挙の結果(令和4年3月27日執行)
- 各種選挙に係る議員等の任期
- 第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査の結果
- 北見市長選挙の結果(令和元年9月8日執行)
- 第25回参議院議員通常選挙の結果(令和元年7月21日執行)
- 北海道知事選挙の結果(平成31年4月7日執行)
- 北海道議会議員選挙(北見市選挙区)の結果(平成31年4月7日執行)
- 北見市議会議員選挙の結果(平成30年3月25日執行)
期日前投票・不在者投票・在外投票・体が不自由な方のための投票
選挙制度等
募集・申請
その他
公園
北見の公園
端野の公園
常呂の公園
留辺蘂の公園
その他
緑化審議会
広報
広報きたみ
端野自治区
常呂自治区
留辺蘂自治区
その他
マイナンバー
マイナンバー
申請・手続き
その他
公的個人認証サービス